フランソワ・トリュフォー論集の刊行
4月下旬にWiley-Blackwellから出版されたダドリー・アンドリューとアンヌ・ジランの編纂によるフランソワ・トリュフォー論集に、「トリュフォーと写真的なもの――映画、フェティシズム、死」と題した論考を寄せた(ちなみに、わたしの章の末尾に「サリー・シャフト翻訳」と書かれて、あたかもフランス語から英語に翻訳されたかのようになっているのは編集段階のミスで、論考はもともと英語で書かれたことを明記しておく)。
Junji HORI, "Truffaut and the Photographic: Cinema, Fetishism, Death", in Dudley Andrew and Anne Gillain (eds), A Companion to François Truffaut, Wiley-Blackwell, 2013, pp.137-152.

A Companion to François Truffaut (Wiley Blackwell Companions to Film Directors)
- 作者: Dudley Andrew,Anne Gillain
- 出版社/メーカー: Wiley-Blackwell
- 発売日: 2013/04/22
- メディア: ハードカバー
- この商品を含むブログを見る
同じシリーズではすでにヒッチコック、ミヒャエル・ハネケ、ファスビンダー、ウッディ・アレンなどが取り上げられているが、トリュフォーの巻とほぼ同時に、ペドロ・アルモドバル、ジャン・ルノワール、ルイス・ブニュエル、フリッツ・ラングなどの巻も刊行されるようだ。どの巻も30本程度の書き下ろしの論文を収録した大部の書物であり(そのため値段も目玉が飛び出るほどだが)、当該作家の研究にとって不可欠なシリーズとして定着しつつあると言ってよいだろう。
トリュフォーに関しては、これまでかなり多くの文献が出版されている。なかでも、アントワーヌ・ド・ベックとセルジュ・トゥビアナによる伝記(Antoine de Baecque et Serge Toubiana, François Truffaut, Gallimard, 2001〔稲松三千野訳『フランソワ・トリュフォー』、原書房、2006年〕)は、良くも悪くも、トリュフォー研究の必読書であろう。トリュフォーの人生と仕事が、冷静な筆致で詳述されていて有益な情報が惜しみなく提供されている反面、見ようによっては血の通わぬ、官僚的な資料の羅列のような印象もぬぐえない本で、特に、生前のトリュフォーと交流のあった世代からは、あまり評価されていないような気がする。とはいえ、本書はそもそも、トリュフォー研究が陥りがちな「人間トリュフォー」への湿った肩入れから意図的に距離を取ろうとしたものとも思われ、その点は積極的に評価できると思う。

- 作者: アントワーヌ・ド・ベック,セルジュ・トゥビアナ
- 出版社/メーカー: 原書房
- 発売日: 2006/03/16
- メディア: 単行本
- 購入: 1人 クリック: 6回
- この商品を含むブログ (15件) を見る
ド・ベックはトリュフォー事典(Le Dictionnaire Truffaut, Editions de La Martinière, 2004)の編纂者でもある。300以上のエントリーの選択はおおむねバランスの取れたもので、標準的な見解が書き記されているが、エントリーによってはさらなる探究のヒントとなるような刺激的な着想が含まれている。また、類書として同じド・ベックの編纂によるモリース・ピアラ事典(Le Dictionnaire Pialat, Léo Scheer, 2008)やジャン・ユスターシュ事典(Le Dictionnaire Eustache, Léo Scheer, 2011)もあり、特に後者は、ユスターシュ周辺の人脈や状況の方が相対的に知られていないこともあって、読み物としてはいちばん面白い。
その他、トリュフォーを論じた書籍としては、シリル・ネイラの入門書(Cyril Neyrat, François Truffaut, Cahiers du cinéma, 2007)は、簡潔にして要を得た内容で信頼できる。トリュフォーと同世代の映画批評家ジャン・コレは、邦訳もあるゴダール論で知られるが、2冊のトリュフォー論も著しており(Jean Collet, Le Cinéma de François Truffaut, Lherminier, 1977とJean Collet, François Truffaut, Lherminier, 1985)、大部の前者はいささか退屈だが、コンパクトにまとまった後者はなかなかおもしろい。作品別に気づいた点をメモしたような本にすぎないのだが、啓発的な着眼点に充ちている本だと思う。ジャン・コレがおもしろいのは、彼のトリュフォー論が、「人間トリュフォー」を括弧に入れて、もっぱら作品の水準に焦点を当てているからだ。だが、同じ方向性で書かれた論考としては、カイエ・デュ・シネマの「作家」シリーズの1冊として書かれたキャロル・ル・ベールのトリュフォー論の方がずっと綿密な作業をしている(Carole Le Berre, François Truffaut, Cahiers du cinéma, 1993)。彼女のTruffaut au travail(Truffaut at Work)も、このシリーズの他の多くの巻と同様、すぐれた成果であると言える。
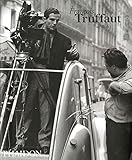
- 作者: Carole Le Berre
- 出版社/メーカー: Phaidon Press
- 発売日: 2005/12/01
- メディア: ハードカバー
- クリック: 18回
- この商品を含むブログを見る
もちろん、「人間トリュフォー」を抜きにしては、トリュフォーの全体像を描けないことも事実であるし、それどころかトリュフォーの作品は彼の人生と切っても切れない関係にあるという立場もありうる。もうじき英訳が刊行されるアンヌ・ジランのトリュフォー論(Anne Gillain, François Truffaut, le secret perdu, Hatier, 1991)は、そのような立場の代表的な研究であろう。トリュフォー自身が、とりわけ「アントワーヌ・ドワネルもの」で、自伝的なエピソードをふんだんにフィクションの材料としているのだから、ことさらにそのような立場を退ける必要もないだろう。

François Truffaut: The Lost Secret
- 作者: Anne Gillain,Alistair Fox
- 出版社/メーカー: Indiana University Press
- 発売日: 2013/07/18
- メディア: ペーパーバック
- この商品を含むブログ (1件) を見る
以上のような見取り図に照らすと、日本の誇る山田宏一の一連のトリュフォー関連書は、一方で彼がトリュフォーの映画的人生のある時期からの同伴者でもあったことから、必然的に、「人間トリュフォー」と彼が生きた文化的コンテクストを重点的に取り上げるものであると同時に(『トリュフォー、ある映画的人生』)、彼の作品に対して愛情にみちた繊細なまなざしを向けてもいる(『フランソワ・トリュフォー映画読本』や『フランソワ・トリュフォーの映画誌』)。わたしもご多分に漏れず、山田宏一の著作に導かれてトリュフォーの世界に足を踏み入れた者のひとりであり、長らく、トリュフォーに関しては、みずから研究の対象とするよりも、山田宏一の幸福感にみちた筆致に心地よく浸るだけで十分だと考えていた。
しかし、実際にトリュフォーを見て受ける総体的な印象と、山田宏一の著作を読んで受ける多幸感や高揚感とが、どうもぴたりと一致しないことが、たびたび気にかかるようになってきた。彼の情愛にみちたまなざしは、シネフィル的なインターテクスチュアリティに対する感度の高さゆえに、トリュフォーを「映画の共和国」の幸福な住人に仕立て上げるようなまなざしであって、ひょっとしたら、トリュフォーの別の側面をかえって見えなくしてしまっているのではないか。
そんな気がしていたときに、セルジュ・ダネーが『隣の女』評で、2人のトリュフォーがいると喝破していることを知った。「尊敬すべき」で「きちんとした」トリュフォー‐ジキルが、広い意味での「家族」を再構築しようとするのに対して、「反社会的、孤独、平静を装いながら情熱的で、フェティシスト」のトリュフォー‐ハイドは「偏狭で私的な情熱」を成就させようとする、と(Serge Daney, "La Femme d'à-côté," in Ciné journal, 1981–86, Cahiers du cinéma, 1986, p.39-41)。この二分法を借りるなら、これまで日本では、トリュフォー‐ハイドの側面が、あまりにも等閑視されてきたのではないだろうか。
拙論の出発点は、以上のような感触である。トリュフォーにおける「写真」のモチーフを通覧する作業を通じて、一見晴れやかな彼の世界が、実のところ、やむにやまれぬ渇望に突き動かされ、フェティシズム的な執着と切り離せず、死の欲動が蠢く世界でもあることを示すこと。その目論見が拙論である程度までは実現できていることを願うばかりである。









