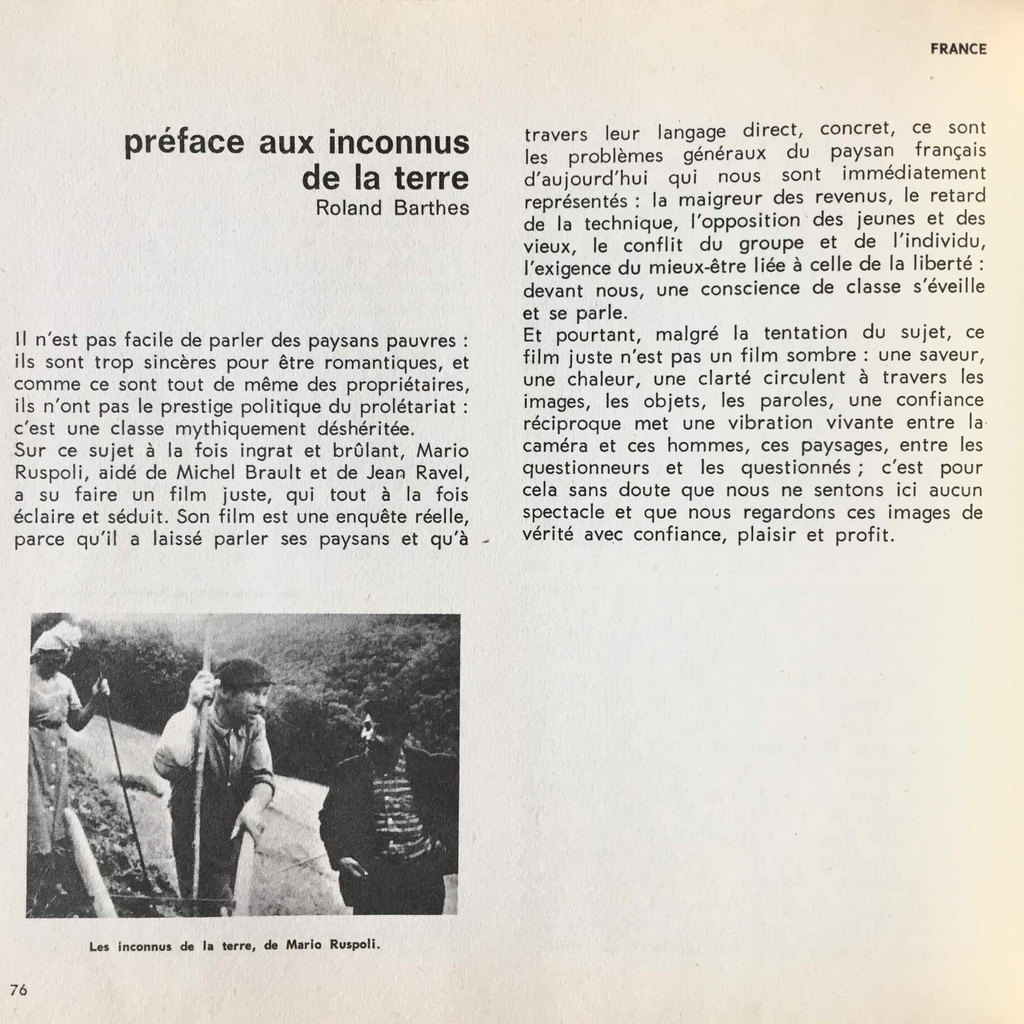ロラン・バルトの未邦訳の映画論
ロラン・バルトと映画の関係については、日本では『ロラン・バルト映画論集 (ちくま学芸文庫)』や『映像の修辞学 (ちくま学芸文庫)』といった独自のアンソロジーによって、比較的よく知られていると思う。『戦艦ポチョムキン』のスチル写真を論じた「第三の意味」や、ユニークな映画館論である「映画館を出て」といったテクストを白眉とする彼の量的にさほど多くはない映画・映像論も、そのほとんどが邦訳されている。
だが、管見の限り一篇だけ、未邦訳にとどまっているばかりか、仏語版の全集に収められてすらいないテクストがあり、ここでその試訳をお目にかける。これはマリオ・ルスポリ(1925-86)監督がロゼール県の農民たちを被写体にして撮った『大地を耕す無名の人々』Les Inconnus de la terre (1961)をめぐる寸評である(ただし、これは文字通りの寸評であり、これを読んでバルトの映画観が更新されるといった類いのものではないことをお断りしておく)。
このイタリア出身のドキュメンタリー作家は、クリス・マルケルと共同製作した捕鯨についての作品『鯨ばんざい』Vive la baleine (1972)で最もよく知られているだろう(この短篇は、ここで視聴できる)。なおマルケルは、ルスポリの最初の短篇『鯨の人々』Les hommes de la baleine (1956)にもコメンタリーを提供している。
ルスポリは、『狂気についての眼差し』Regard sur la folie (1962)で、初めて精神病院の中にカメラを持ち込んだとも言われており(たしかにフレデリック・ワイズマンの『チチカット・フォーリーズ』にも5年先駆けている)、ジャン・ルーシュ、ミシェル・ブロー、ピエール・ペローなどと並んで、いわゆる「シネマ・ヴェリテ」の重要な担い手と目されている。その全貌は、フランスでは以下のDVDで手軽に確かめることができる。
バルトによるこの短評の存在は、フィリップ・ワッツの遺稿に基づいて編まれた好著Le cinéma de Roland Barthes : Suivi d'un entretien avec Jacques Rancièreに「付録」として再録されているのを読んで知った(本書には、英語版Roland Barthes' Cinema (English Edition)もある)。初出は、映画公開時にアルゴス・フィルムが作成した冊子であるそうだが、わたしが確認できたのは、『Artsept』誌の「映画と真実」特集号への再録である(Artsept, nº 2, avril/juin 1963, p.76)。該当ページの写しを本エントリー末尾に掲げておく。ちなみに本誌は、まだ20代だったレーモン・ベルールが1963年にリヨンで創刊した雑誌で(3号で終刊)、この第2号はヴェルトフ、イヴェンスに始まり、ロバート・ドリュー、リーコック、フリー・シネマ、ルーシュ、ルスポリ、マルケルなどを取り上げている。
マリオ・ルスポリ『大地を耕す無名の人々』への序言
堀潤之訳
貧農について語るのは容易なことではない。彼らは誠実すぎて物語の主人公にはなれないし、そうは言っても地主なので、プロレタリアートとしての政治的威信も持っていない。彼らは神話的なまでに恵まれない階級なのである。
この報いるところの少ない、厄介な主題について、マリオ・ルスポリは、ミシェル・ブローとジャン・ラヴェルの助力を得て、公正な映画を作ることができた。啓発的にして魅惑的な映画である。彼の映画は、現実に行われた調査である。というのも、ルスポリは農民たちに語らせており、彼らの直接的で具体的な言語を通じて、今日のフランスにおいて農民が抱えている一般的な諸問題が指摘されるからだ――つまり、収入の乏しさ、技術の遅れ、若者と老人の対立、集団と個人の衝突、生活条件の改善への要求と結びついた自由への要求。私たちの目前で、階級意識が芽生え、みずからを語るのである。
しかしながら、この公正な映画は、主題の誘惑にもかかわらず、陰鬱な映画ではない。ある味わい、熱烈さ、明晰さが、映像、事物、台詞を通じて行き交っており、相互的な信頼が、カメラと人物や風景の間、質問する側と質問される側の間に生き生きとした震えをもたらしている。私たちがここで何も見世物であるとは感じず、これら真実の映像を信頼と悦びと有益さをもって眺めるのは、おそらくそのためである。