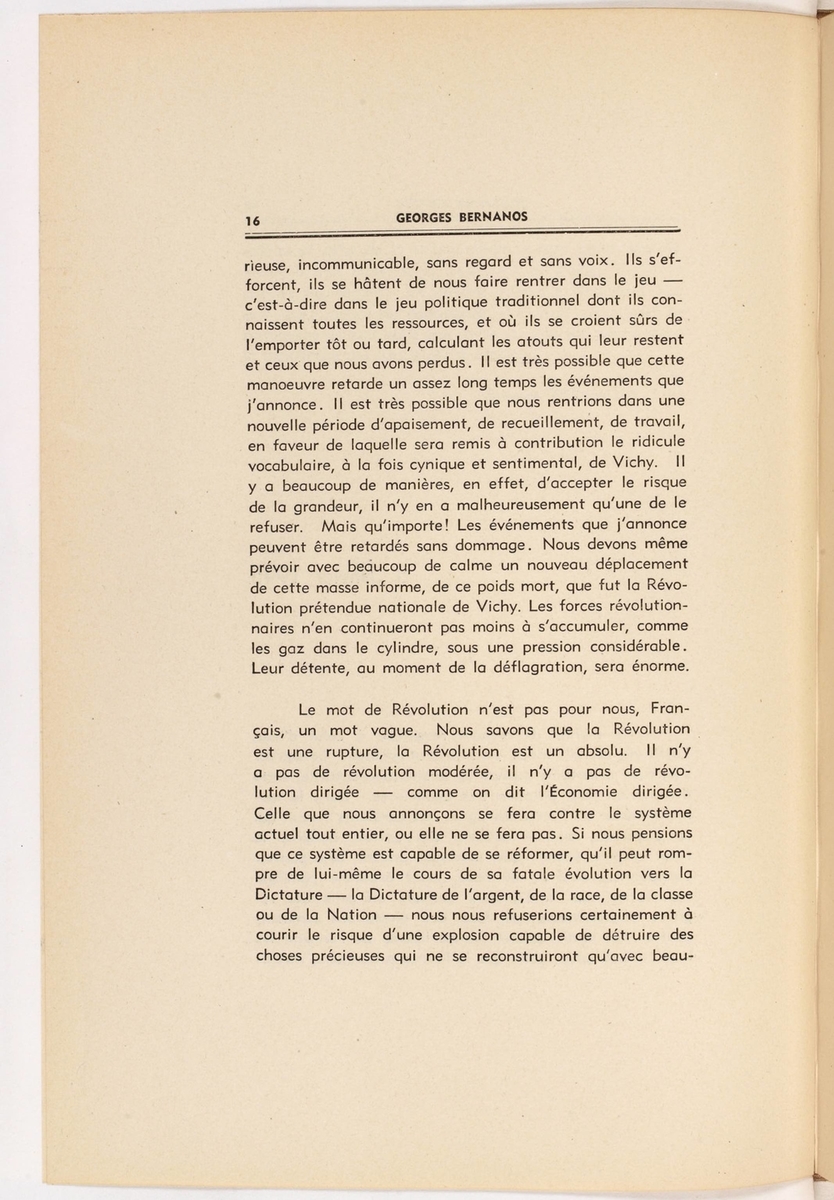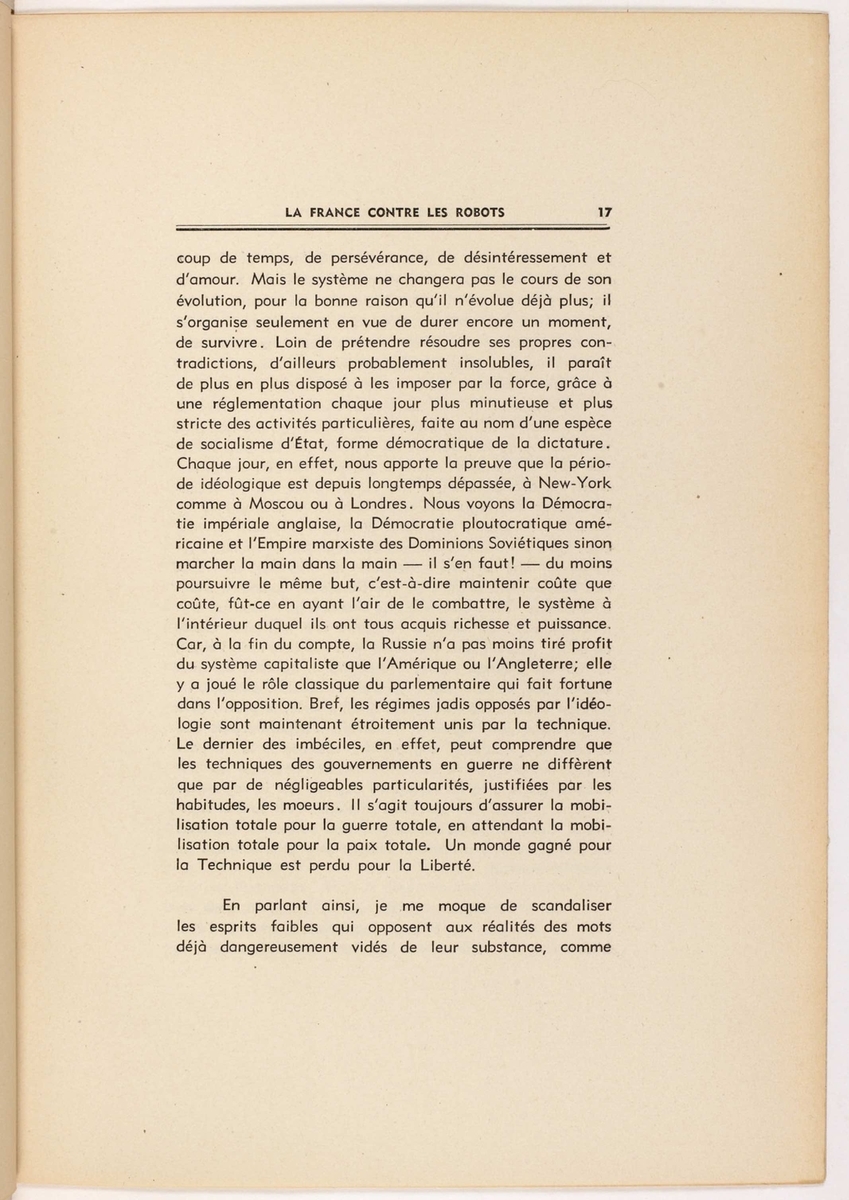ストローブの新作『ロボットに対抗するフランス』(2020)に寄せて
以下に訳出するのは、ジャン゠マリ・ストローブの約9分間の新作短篇『ロボットに対抗するフランス』La France contre les robots (2020)で読み上げられている文章である(この短篇は、4月5日にKino Slangで公開され、現在では製作元Belva FilmsのYouTubeチャンネルでも見ることができる)。
作品内でクリストフ・クラヴェールが朗唱するこのテクストは、作家ジョルジュ・ベルナノス(1888-1948)が移住先のブラジルで1945年に執筆し、翌年に刊行された同名の評論の一節である(第1章の第2パラグラフの全体が使われている)。原書はフランス国立図書館のGallicaで入手できるが、管見の限り、邦訳はなされていない。
映画の文脈でベルナノスといえば、何と言っても、ロベール・ブレッソンの『田舎司祭の日記』(1951)の原作者であるカトリック小説家として知られていよう(もちろん、同じくブレッソンの『少女ムシェット』(1967)とモーリス・ピアラの『悪魔の陽の下に』(1987)も忘れてはならない)。ストローブとダニエル・ユイレが、まだ一本も映画を撮っていない1954年の時点で、ベルナノスの初期の作品『影の対話』Dialogue d’ombres(三輪秀彦訳、『世界の文学52 フランス名作集』所収、中央公論社、1966年)の映画化という企画を温めていたのも、おそらくブレッソンの映画の影響だろう。それからおよそ60年を経た2013年、ストローブはそのフィルモグラフィーで初めてベルナノスに依拠した作品として、約30分の短篇『影の対話』を仕上げることになる。
こうした事情を踏まえると、ベルナノスはストローブ゠ユイレの潜在的な関心の対象であり続けていたのかもしれない。だが、この二人の映画作家がブレヒト、パヴェーゼ、ヴィットリーニといった左派の作家たちを繰り返し取り上げてきたことを思うと、ベルナノスという選択はやや意外にも響く。というのも、ベルナノスは、若くしてシャルル・モーラス率いる極右王党派のアクシオン・フランセーズに心酔し、反ユダヤ主義の奇書『ユダヤ的フランス』の著者エドゥアール・ドリュモンについての評伝『良識派の大いなる恐怖』(La Grande peur des bien-pensants, 1931)を書いたかと思えば、スペイン内戦に際して『月下の大墓地』(邦訳は春秋社の『ベルナノス著作集』第4巻所収)を書いて反ファシズムの立場に鞍替えし、その後7年間にわたって南米で暮らしたという、イデオロギー的には捉えがたい人物だからである。
たとえば、フランスの歴史家ミシェル・ヴィノックの『知識人の時代』(塚原史・立花英裕・築山和也・久保昭博訳、紀伊國屋書店、2007年)では、彼の政治的立場は次のようにまとめられていて、ストローブ゠ユイレの世界の一画を占めるにふさわしいとはあまり思えないのも事実である。
この作者の立場は独自のものであり、さらには唯一のものであった。キリスト教系民主主義者の一族にも、また保守派右翼にも与せず、かといって『エスプリ』を中心に生まれ、発展しつつあったこの左翼カトリックにより一層近づくこともなかったベルナノスが忠実であろうとしたのは、自分の起源である王党派と、反ユダヤ主義の老いた師ドリュモン、そして自由の精神がしっかりと存在していた古きフランスという夢であった。(344頁)
ストローブが今回取り上げている小冊子『ロボットに対抗するフランス』も、全体としては、機械文明の批判が骨子であり、近代における機械への隷属と人間のロボット化に対抗して、「精神的な革命」、すなわち「世界のなかで精神的なもろもろの力があらたに炸裂する必要」を訴えるというのが基本的な構図となっている(ただし、いま引いた語句は、『著作集』第6巻に邦訳が収められている小文「ロボット的人間の横行する病める世界において、フランスは精神の蜂起ののろしを上げるであろうか?」(渡辺義愛訳)から取った)*1。
おそらく、こうしたコンテクストを真正直に踏まえる必要はないのだろう。実際、以下の引用箇所だけを切り離して読めば、左右の政治的イデオロギーに立脚せず、資本主義と結託した〈技術〉の支配に対して強烈な「否」を突き付ける身振りが、力強くせり上がってくる。ベルナノスは「戦後」のヨーロッパ精神の腐敗に対して、歯に衣着せぬ苛烈な批判を放ち、四面楚歌になったという(『著作集』第6巻の渡辺一民による解説を参照)。孤立を懼れない根底的な抵抗の身振りに倣おうとするストローブは、依然として意気軒昂であるようだ。
〈革命〉という言葉は、我々フランス人にとって、漠然とした言葉ではない。我々は〈革命〉がひとつの断絶、ひとつの絶対であることを知っている。穏健な革命や、計画経済と言うときのように計画された革命などというものは存在しない。
我々が予告する革命は、現下のシステム全体に対抗してなされるか、さもなければまったくなされないだろう。もしこのシステムが自らを正すことはありうる、つまり〈独裁〉――金銭の、人種の、階級の、あるいは〈国家〉の――へと向かって行く避けがたい進展の流れをおのずから断ち切ることができる、と考えるのであれば、我々はもちろん、爆発的変化[une explosion]のリスクなど冒そうとはしまい――それはかけがえのない物事を破壊しかねず、破壊されたものは長い時間と辛抱強さと無私無欲と愛をもってしか元通りにならないだろうから。
だが、システムはその進展の流れを変えることはないだろう。すでにもはや進展していないからである。システムはそれがもう一瞬間続くこと、生きながらえることだけを目指しておのれを組織しているのだ。
システムは、それに固有の矛盾の数々を解決すると言うどころか――そんな矛盾はそもそも解決不可能なのだろう――、ますますそれらを力づくで押し付ける気でいるようだ。それも、独裁の民主主義的形態たる一種の国家社会主義の名の下で、個別の活動に関してなされる規制が、日ごとにより入念かつ厳密になっていくおかげである。
実際、日ごとに我々のもとに届けられる証拠が、ニューヨークでもモスクワでもロンドンでも、イデオロギーの時代がかなり前から古びていることを示している。我々が目の当たりにしているのは、イギリスの傲然たる民主主義、アメリカの金権政治にまみれた民主主義、ソヴィエト各領土からなるマルクス主義帝国が、手に手を取って歩んでいるとは言わないまでも――とんでもない!――、少なくとも同じ目的を追求しているさまだ。すなわち、どの体制もシステムの内側で富と権力を獲得した以上、システムに対抗しているようにみえようとも、実は何が何でもシステムを維持しようとしているのだ。
というのも、結局のところ、ロシアはアメリカやイギリスに劣らず、資本主義のシステムから利益を得たからだ。反対派に属することで財をなすという国会議員の古典的な役割を果たしたわけである。
要するに、かつてイデオロギーによって対立していた体制どうしが、いまや技術によって緊密に結びついている。実際、どんな愚か者でも理解できるように、戦争状態にある政府が用いる技術は、風俗習慣によって説明のつく些細な個別事情によってしか違わない。
総力平和に向けた総動員を待ちながら、総力戦に向けた総動員を保証することがつねに問題になっている。〈技術〉にとっては勝ち取られた世界でも、〈自由〉にとっては敗北なのである。
- 原文(以下参照)ではこの抜粋全体で一つの段落を構成しているが、ここではウェブ上での読みやすさを優先し、適宜改行を施した。