ゴダールの『イメージの本』覚書(1) イントロダクション
以下に掲載するのは、ラジオ関西の30分の番組「シネマキネマ」で2019年4月27日27時から放送された内容のうち、わたしが語った部分の書き起こしである(一部、補足した箇所もある)。
全体がゴダールの新作紹介にあてられたこの回では、『イメージの本』の全体像を大づかみに理解できるようなイントロダクション的な内容を目指したつもりである。
取材時にわたしがたどたどしく語った内容は、番組ディレクターの吉野大地氏の「手」によって巧みな編集を施されており、さも淀みなく語り下ろした格好になっている(ゴダールに倣って、切り貼りした「手」の触感が残るような、ざらついた編集にあえてしたという!)。また、実際の番組では、採録部分に先だってナヴィゲーターの山本せりか氏による導入があり、セクション毎にも的確な合いの手が差し挟まれている。両氏には最大限の感謝を捧げたい。番組のご厚意で、ここでは割愛したナレーション部分を含むポッドキャスト版を特別に作っていただいたので、ぜひ改めてお聞きいただきたい。
なお、昨年、『イメージの本』の本篇の公開前に予告篇だけを見て書いた本ブログの記事「ゴダール新作『イメージの本(Le Livre d'image)』予告篇についての覚書」もある。また、今回ラジオで語った内容をさらに発展させた『イメージの本』論を、批評誌『ヱクリヲ』10号に「ピクチャレスク・ゴダール――『イメージの本』における「絵本」の論理」として寄稿している。これらも併せてお読みいただければ幸いである。

ヱクリヲ vol.10 特集I 一〇年代ポピュラー文化――「作者」と「キャラクター」のはざまで 特集II A24 インディペンデント映画スタジオの最先端
- 作者: 高井くらら,横山タスク,伊藤元晴,山下研,さやわか,西兼志,得地弘基,難波優輝,楊駿驍,横山宏介,堀潤之,小川和キ,伊藤弘了,佐久間義貴,村井厚友,福田正知
- 出版社/メーカー: エクリヲ編集部
- 発売日: 2019/05/10
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
「手で考える」
『イメージの本』(2018)の冒頭ではゴダール自身のナレーションで、次のようなことが語られます。「5本の指があって、指が合わさると手ができて、そして人間の真の条件とは手で考えることだ」という、少し謎めいたナレーションからこの映画が始まるんですね。手で考えるとはどういうことなのか、それは端的に言えば編集するということです。実際の映画の冒頭部分がどういう映像の連なりになっているのかというと、まず映画のメインビジュアルでもあるダ・ヴィンチが描く《洗礼者ヨハネ》の天を指し示す指が出てきて、次いでフィルム片をモンタージュする手が出てきます――これはゴダール自身の『リア王』(1987)からの引用で、手の主は実はゴダールではなくてウッディ・アレンなんですけれども――。それから、様々な映画から手の映像が引用されて連なっていきます。ジャコメッティの彫刻の手なんかも出てくる。こういう風に既存の映像の断片を編集することで、このプロローグ部分のみならず映画のほぼ全体が出来上がってる。そういう意味で、『イメージの本』は「手で考える」ことを徹底した編集の映画だとまずは言えると思います。


ゴダールは、1998年に完成した『映画史』(1988-98)でも似たような映像のコラージュを行っていました。『映画史』完成後、ゴダールは再び物語を撮るようになって、たとえば『愛の世紀』(2001)でも、『アワーミュージック』(2004)でも、『ゴダール・ソシアリスム』(2010)でも、前作の『さらば、愛の言葉よ』(2014)でも、俳優を使った物語がある程度は展開されていました。今回はそういった物語的な要素がほとんどなく、いわば『映画史』に回帰したようなかたちで、映像のコラージュだけによって映画全篇が作られています。『映画史』に比べると、映像のコラージュの密度はよりシンプルになっていると同時に、かえって力強いものにもなっているように思います。
「5+1」という作品の構造
『イメージの本』は映像のコラージュだけで成り立っていますので、映画の構造を把握することが見るときには重要です。5本の指ということでこの『イメージの本』は5章構成だと思われがちですし、私自身もずっとそう考えてきたんですけれども、いま申し上げたようにゴダールは「5本の指があり、指が合わさると手がある」と言っていますので、実は「5+1」の6セクションから成っているんじゃないかと思います*1。
上映時間としては5本の指を合わせた5つの最初のセクションで前半が構成され、残りの「手」の部分である6番目のセクションでだいたい後半が構成されています。『イメージの本』の上映時間は84分ぐらいですので、5本の指の部分でだいたい40分強、それから手の部分で同じく40分強あるということになります。
各セクションの主題を簡単に紹介すると、5本の指の一本目は「1 リメイク」と題されていて、映画史が広い意味でのリメイクの連鎖で成り立っていて、現実世界もまた映画のリメイクで成り立っているという仮説が提示されます。
2番目のセクションは「2 ペテルブルク夜話」と題されていまして、ここでの主題はひと言で言うと戦争です。19世紀初頭にカトリックの思想家で反革命の立場をとっていたジョゼフ・ド・メーストルという人がいるんですけれども、この人が書いた『サン・ペテルスブルグの夜話』(1821年刊行)という本がタイトルの由来になっていて、ゴダールはその本の中からド・メーストルが展開する特異な戦争論を引用しています。
第三セクションのテーマは列車です。ここでは様々な映画からの列車のイメージが自由連想に従って繋ぎ合わせされています。ドイツの詩人リルケから取られた、「3 線路の間の花々は旅の迷い風に揺れて」という少し詩的なタイトルが付けられてます。
4番目のセクションはモンテスキューに由来する「4 法の精神」というタイトルです。ここでは、「法」というやや抽象的な概念をめぐる様々な映像の断片が繋ぎ合わされていて、全体としては「法」についての思考が映像のコラージュを通じて展開されています。
5番目のセクションは「5 中央地帯」。これはマイケル・スノウが1971年に撮った伝説的な実験映画からそのままタイトルを取っています。実際、『中央地帯』からの抜粋も最初に出てきますが、ここではソ連のアレクサンドル・ドヴジェンコの『大地』(1930)から、主人公とその許嫁の非常にフォトジェニックな映像が出てきて、このセクションは数分で終わるものと考えられます。
後半を占める6番目のセクション、「手」としてのセクションの主題は「アラビア」で、「幸福のアラビア」という字幕も出てくるのでそれがタイトルであると考えられます。エジプト出身のフランス語の作家アルベール・コスリーの小説『砂漠の中の野望』が長く朗読されるなか、中近東の映画からの多数の引用でもって、アラビアをめぐる一種の映像詩のようなものが展開されるセクションになっています。
1. リメイク
ゴダールは、「リメイク」と「韻を踏むこと」を結びつけています。フランス語で押韻のことをリーム(rime)というわけですが、リメイクとリームを合わせた「RIM(AK)ES」という文字列が第一セクションの途中で出てきます。そのような形で韻を踏むような映像を連想によって繋げていくのがこのセクションのみならず『イメージの本』全体を貫く主たるロジックと言えるでしょう。
このセクションでは、たとえば複数の映画の似たシチュエーションのシーンを結びつける事例もたくさん出てきます。ニコラス・レイの『大砂塵』(1954)の有名なシーンの後にゴダール自身の『小さな兵隊』(1960)の少し似たシチュエーションが出てくる。あるいは、ロベルト・ジオドマーク/エドガー・G・ウルマーの『日曜日の人々』(1930)とジャック・ロジエが撮った短編の『ブルー・ジーンズ』(1958)がシチュエーションの類似性を介して続けて出てきたりします。こういう繋ぎは、通常の意味でのリメイクに近い事例だと思います。
さらに単なる連想に近い繋ぎも、このセクションにはたくさん出てきます。一番目覚ましいのは、水のモチーフを介して、ヒッチコックの『めまい』(1958)とか、フランク・ボーゼーギの『河』(The River, 1929)とか、ジャン・ヴィゴの『アタラント号』(1934)のシーンが連鎖していく箇所でしょう。
しかし、おそらく一番刺激的なのは、現実とフィクションをまたいで何らかの押韻、ないし何らかのリメイクがなされている箇所だと思います。たとえば、セクションの冒頭に原水爆実験の映像が出てくるわけですけれども、それがロバート・アルドリッチの『キッスで殺せ』(1955)のラストシーンにおける忘れがたい爆発と結びつけられる。あるいは、ロッセリーニの『戦火のかなた』(1946)でパルチザンがポー川に突き落とされるシーンに続いて、現在のいわゆるイスラム国の処刑のシーンが続く箇所などがそれに当たるでしょう。
2. ペテルブルク夜話
このセクションで中心的に取り上げられるジョゼフ・ド・メーストルは、フランス革命の時代のカトリックの思想家で、しかも強烈に反革命の立場を取っていた人です。1802年から17年までサルデーニャ王国の外交官のような立場で当時のロシアの首都であるサンクトペテルブルクに派遣されていた人物なんですね。
これまでのゴダールでド・メーストルが引かれたことはおそらくなかったと思いますし、さらに言えばなぜド・メーストルが突然出てくるのか、不思議に思う方も多いと思います。私の考えでは、たぶんトルストイを経由してド・メーストルに行き着いたのではないかと思っています。ゴダールは、『アンナ・カレーニナ』(1873-77)とか『戦争と平和』(1864-69)といった小説をおそらく好んでいて、よく話題に出しますし、トルストイの時代にはド・メーストルは結構読まれていて、実際、彼が『戦争と平和』を執筆していた時にも、かなりしっかりとド・メーストルの本を読み込んでいたと伝えられています。ですから、トルストイを経由してド・メーストルという新たな思想家が出てきたのではないかと思います。実際、このセクションの映像は、セルゲイ・ボンダルチュクの超大作映画『戦争と平和』(1965-67)からいくつかのシーンが引用されることによって始まっています。


このセクションでは、ド・メーストルが『サン・ペテルスブルグの夜話』*2で展開する特異な戦争論が、彼の肖像画なんかも出されながら、比較的丁寧に紹介されていきます。ド・メーストルは、人間を含めた生き物は不可避的に殺戮を行っている、つまり食べるために動物を殺すようなことをどんな生き物も行っている、したがって、大地全体が殺戮の巨大な祭壇であると捉えていて、戦争という行為も世界の法則そのものであるがゆえに神的なものであると考えていました。そのド・メーストルの考えを絵解きするような数々の災厄の映像が、このセクションでは多々引用されていくことになります。アンドレ・マルローの『希望』(1938-39)であるとか、ロッセリーニの『無防備都市』(1945)といった映画も引用されますし、溝口健二の『雨月物語』(1953)で水戸光子が暴行されるシーンもこのセクションに出てきます。
振り返ってみると、『アワーミュージック』の冒頭の10分ぐらいのセクション《地獄篇》も、災厄の映像をたくさんコラージュしたセクションでした。『イメージの本』のこのセクションは、その『アワーミュージック』の冒頭の10分を引き継ぎつつ、そこにド・メーストルという特異な思想家の言説を追加したものと捉えられるでしょう。
3. 線路の間の花々は旅の迷い風に揺れて
このセクションは、列車が出てくる様々な映画からの引用がまさに自由連想によって連なっていく、とても楽しいセクションです。最初の方にジャック・ターナーの『ベルリン特急』(1948)が出てきて、非常に印象的な横移動で登場人物が紹介されていくシーンも出てきますし、映画史の様々な局面から多数の映画が引用されています。日本ではマイナーかもしれませんが、ドキュメンタリー映画の古典的傑作と言われているヴィクトル・トゥーリンの『トゥルクシブ』(Turksib, 1929)という映画があって、このトルキスタン・シベリア鉄道の敷設の模様を描いたドキュメンタリー映画も何箇所かにわたって引用されています。他にも自作からはたとえば『フォーエヴァー・モーツアルト』(1996)の列車のシーンが出てきたり、おそらくゴダールが初めて引用したテオ・アンゲロプロスからは、『霧の中の風景』(1988)で幼い姉と弟が列車に乗り込もうとするシーンが引かれます。ストローブ=ユイレの『シチリア!』(1999)も引かれますし、セクションを締め括るのはマックス・オフュルスの『快楽』(1952)で、都会に戻っていくダニエル・ダリューをジャン・ギャバンが見送るシーンが、非常に壮麗な移動撮影によって捉えられています。
ウィリアム・ウェルマンの1930年代のプレ・コード期の佳作『家なき少年群』(1933)からは、主人公の友人が列車に轢かれて足を切断する羽目になるというちょっと不吉なシーンも出てくるんですが、全体としては列車が映画にもたらす運動感への幸福なオマージュが捧げられているセクションだと思います。
このセクションの大きな特徴としてはもう二つほど挙げられると思うんですけれども、一つは実験映画が多く含まれているということです。ここで引かれている実験映画は、おそらく本作の協力者の一人である映画研究者ニコル・ブルネーズがもたらしたものだと思われ、セクションの冒頭ではアル・ラズティスというカナダの実験映画作家がリュミエール兄弟の『列車の到着』をいわばより迫力があるような形に改作した『リュミエールの列車』(Lumière's Train, 1979)という映画が引かれています。ちなみに、それに先立ってホームにいる女の子が到着する列車を見て驚くショットが差し挟まれていますので(後にこのホームビデオからの映像だと知った)、これはリュミエール兄弟の『列車の到着』を見た当時の観客が、現実の列車と取り違えて思わず逃げ出したという有名な神話を踏まえているのでしょう。またセクションの最後の方では、イームズ夫妻の『おもちゃの汽車のトッカータ』(1957)とかジャック・ペルコントというフランスの若手の実験映画作家の『火の後』(Après le feu, 2010)という映画も引かれています。この『火の後』は、列車の先頭から捉えた映像が次第にサイケデリックな色調に変化していくという実験映画なんですけれども、列車がもたらす知覚の変容――そもそも列車が登場したときに、人々は列車がもたらす知覚に驚いたわけですが――を現代風に再び考察したもののようにも思われます。ゴダールが実験映画を引用することはこれまであまりなかったんですけれども、他の古典的な映画と違和感なくうまく溶け込んでいる印象を持ちました。


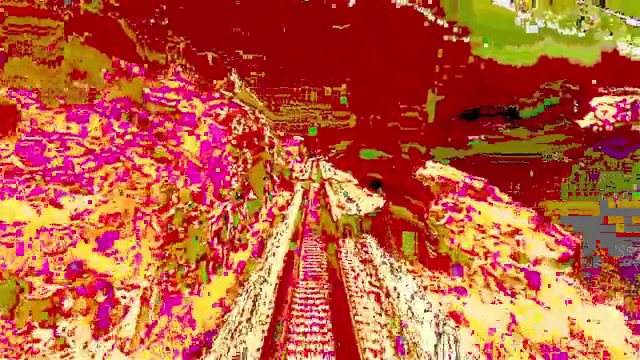


4. 法の精神
このセクションは、私の考えでは第二セクションと対になっているものです。ジョゼフ・ド・メーストルが戦争を「世界の法則」とみなしたのに対して、ここでゴダールはモンテスキューを梃子にして、別種の「法」がありうるのではないか、という考察を試みているのだと思います。つまり、世界の悲惨さをただ是認するような「法則」ではなく、暴力を制御するものとしての「法」を新たに制定することに関心が寄せられているのではないか。
だからこそこのセクションでは、様々な次元の「法」にまつわる映像のコラージュが展開されるなかで、特に「革命」の契機に重点が置かれています。「革命」とは、それまでの「法」を廃棄して、新たな「法」を作り上げるという出来事でもあるからです。実際、このセクションは1871年のパリ・コミューンを疑似ドキュメンタリー的に再構築したピーター・ワトキンスの映画『ラ・コミューン(パリ、1871年)』(La Commune (Paris, 1871), 2000)で始まり、後半ではテレビ映画から取られたロベスピエールの演説が登場する。ほかにも、たとえば反マクロン・デモの様子をとらえたニュース映像や、ソ連の反体制的な歌手ウラジーミル・ヴィソツキーがしゃがれ声で歌う《オオカミ狩り》といった要素も、「革命」とまでは言えないものの、既存の「法」の支配から逃れようとする動きを表していると解釈できます。
以上を踏まえますと、このセクションで最も印象的な引用は、ジョン・フォードの『若き日のリンカーン』(1939)ではないかと思います。ヘンリー・フォンダ演じる若きエイブラハムは、通りすがりの一家から樽に入った書物一式を譲り受けて、その中にたまたま入っていた法律書に興味を惹かれ、ゼロから「法」を発見していくことになる。ゴダールがここでやろうとしているのも、まさに同じこと、つまり「法」の別のあり方をゼロから探っていくことであるように思われます。
5. 中央地帯
ゴダールによれば、このセクションのテーマは「男女間の愛」ということになっています。これは非常に意外な感じがします。というのも、セクションの冒頭で引かれるマイケル・スノウの実験映画は、男女間の愛とは何の関係もないからです。しかし、ゴダールはどうやら本気で、「愛」(ここでの「愛」は異性愛に限られるのですが)こそが人間にとっての「中央地帯」であると考えているふしがあります。
実際、ゴダールのフィルモグラフィを振り返ってみますと、彼にはベタな意味でリリカルな側面があると思います。長篇第一作の『勝手にしやがれ』(1959)にしても、1980年代の傑作『カルメンという名の女』(1983)にしても、ストーリーとしては男女の愛の不可能性がテーマになっているわけです。
 『イメージの本』のこのセクションの中心を占めているドヴジェンコの『大地』のカップルも、実は同じテーマに連なっています。というのも、ここで引かれているのは主人公の男とその腕の中にいる許嫁を交互に捉えたフォトジェニックな映像ですが、元々の『大地』のストーリーでは、このカップルの男の方は、すぐ後のシーンで何者かに射殺され、女の方はそれが原因で気が狂ってしまいます。こうしたストーリー展開を踏まえれば、これは成就することのない愛なわけです。
『イメージの本』のこのセクションの中心を占めているドヴジェンコの『大地』のカップルも、実は同じテーマに連なっています。というのも、ここで引かれているのは主人公の男とその腕の中にいる許嫁を交互に捉えたフォトジェニックな映像ですが、元々の『大地』のストーリーでは、このカップルの男の方は、すぐ後のシーンで何者かに射殺され、女の方はそれが原因で気が狂ってしまいます。こうしたストーリー展開を踏まえれば、これは成就することのない愛なわけです。
もう一つ、この『大地』のカップルが、『イメージの本』の中では上映時間にしてちょうどほぼ真ん中に位置していて、いわば本作の「中央地帯」を占めていることも付け加えておきたいと思います。
幸福なアラビア
これまでのゴダールにおいて、アラブといえばパレスチナのことでした。ゴダールは1970年にパレスチナで映画を撮ろうとして以来――その映画は困難な編集過程を経て、およそ5年後に『ヒア&ゼア』という重要作として結実する――、今に至るまでずっと親パレスチナ的で反シオニズム的な立場を取っており、そのせいで時おり反ユダヤ主義者という言いがかりをつけられてもいる人なんですね。
ところが、『イメージの本』では、わずかに『ヒア&ゼア』(1974)からマフムード・ダルウィーシュの詩を朗読する少女の声が引かれるくらいで、それを除けばパレスチナはほとんど出てこない。
では、この作品のアラビアとは何なのか、ということですけれども、ひと言で言えば、劇中に何度も引用されるパゾリーニの『アラビアン・ナイト』(1974)のようなアラビアなのではないかという気がします(以下の写真は、同作品よりの数々の引用)。つまり、「千夜一夜物語」的な、いわばお伽のようなアラビア、さらに言えば、現実から遊離した「幻想のアラビア」が形作られているのではないか、という気がするんですね。





といいますのも、確かにこのセクションではオーセンティックな、チュニジアをはじめとするマグレブの映画も引かれていますし――たとえば、ナーセル・ヘミールの作品は幾つも引かれています――、エジプトのユーセフ・シャヒーンも引かれ、シリアの巨匠と言われるモハマッド・マラスの作品も引かれている。でも、それと同時に、アラビア世界を舞台にした西洋の映画も引かれていて、それらが混ぜ合わせられているわけです。そうした意味で、オーセンティックなアラビア映画を引いてはいるものの、ゴダールが表象するアラビアがどうしても「幻想のアラビア」のように見えてしまうということがあると思います。
ゴダールはこのセクションの中で、エドワード・サイードを引用しています。サイードはかつて『オリエンタリズム』で、西洋がイスラム世界を中心とする非西洋に誤解に満ちた眼差しを投げかけていることを批判したわけです。しかし、ここでのゴダールのアラブ世界の扱いは、サイードが批判したオリエンタリズム的な視線を免れていないのではないか、という気もします。
とはいえ、ゴダールが『イメージの本』のために、比較的新しい中近東の映画を大量に見て、それをみずからのコーパスに取り入れようとしたことは間違いありません。かつてゴダールが20世紀末に仕上げた『映画史』には、ゴダール以降の映画はほとんど出てこないことで批判されもしましたが、それに比べると、80歳代後半のゴダールがここからさらに新たなスタートを切ろうとしていることには感銘を受けざるをえません。
*1:以下にみるように、5本の指に相当するセクションには番号が振られ、「手」としてのセクションには番号が振られていないので、本作を5部からなると考える方がむしろ自然である。しかし、本作の密接な協力者であるファブリス・アラーニョも、ニコル・ブルネーズも、本作は6セクションからなると明言している(それぞれのリンク先の動画を参照)。
*2:原書は、フランス国立図書館のGallicaで各版が閲覧可能(https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6537390v)。半世紀前の邦訳(https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA45365265)は入手困難だが、国立国会図書館デジタルコレクションで、図書館向けデジタル化資料送信サービスが利用できる(http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1708159)。